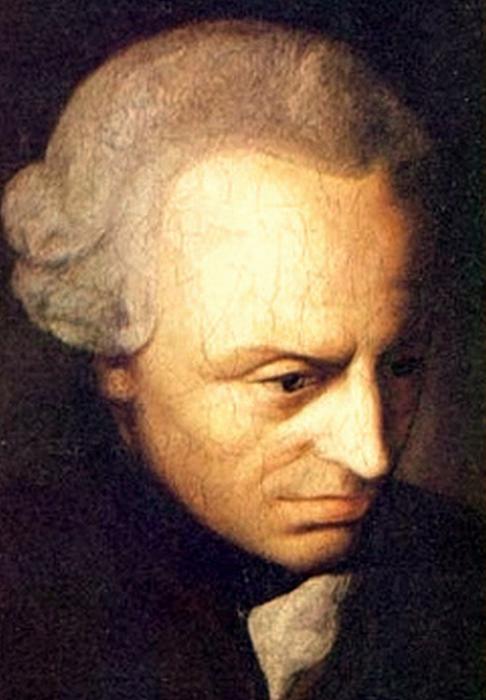哲学における真実の問題は中心的です知識の理論全体で。それは本質そのものと同一視され、最も重要な世界観の概念の1つであり、善、悪、正義、美などの重要な現象と同等です。
哲学と科学における真実の問題はかなり複雑です。過去の多くの概念、たとえば、原子の不可分性に関するデモクリトスの概念は、ほぼ2000年の間議論の余地がないと考えられていました。今ではそれはすでに妄想として提示されています。しかし、おそらく、既存の科学理論の大部分は、時間の経過とともに反駁される妄想であることが判明するでしょう。
その発展のあらゆる段階で、人類は相対的な真実だけを持っていた-妄想を含む不完全な知識。相対的な真実の認識は、世界を認識するプロセスの無限大、その無尽蔵と関連しています。
哲学における真実の問題もそれぞれの歴史的時代の知識が絶対的な真実の要素を含んでいるという事実は、それが客観的に真実の内容を持っているので、認識の必要な段階であり、次の段階に含まれます。
解釈の方法
哲学における真理の問題は、その解決のためにこの概念を解釈するいくつかの方法を必要としました。
- オントロジーの理解。 「真実は何であるかです。」物や物の存在そのものが重要です。結論の正しさはある瞬間に明らかになり、人は言葉や芸術作品を通してそれを開き、それによってそれをすべての人の所有物にします。ただし、同じプロセスの理解と認識が異なる場合、この立場は重要ではありません。
- 認識論的理解。「真実とは、知識が現実に対応するときです。」しかし、ここでは、明らかに比類のないものを比較する慣行が広まっているため、多くの意見の不一致も生じます。また、「自由」「愛」など、多くの現象を検証することはできません。
- 実証主義者の理解。「真実は経験によって確認されなければなりません。」実証主義は、実際に実際にテストできるものだけを考慮し、残りは「真の哲学」の研究を超えました。そのようなアプローチは、人にとって重要な多くの現象、プロセス、およびエンティティを明らかに無視します。
- 語用論的理解。 「真実は知識の有用性、有効性です。」このアプローチによれば、正しいものは効果をもたらし、利益をもたらすものとして認識されました。
- 従来の理解。「真実は合意です。」このアプローチによれば、意見の不一致が生じた場合、正確に正しい結論と見なされるものについて合意する必要がありました。このポジションは特定の期間のみ使用でき、すべての活動領域で使用できるわけではありません。
哲学における真実の最もありそうな問題これらすべてのアプローチを組み合わせます。真実は実際に存在するものであり、私たちの知識に対応しています。同時に、それは明確な契約、合意です。それは客観的かつ主観的、絶対的かつ相対的、具体的かつ抽象的です。
認知活動に大きな価値人の信仰、信念、自信を演じます。認知の過程で、対象は世界に近づき、それと融合します。認知関係は興味のある関係であり、無関心や非人格性ではありません。認知過程では、信仰と信念の意志の選択があります。実際、信仰は知識の出発点であり、その目標です。それはあなたが無知と知識の間に存在するギャップを埋めることを可能にします。哲学における真実の問題は、より説得力のある説明を選択することにあります。したがって、正確な証拠や情報の欠如の中であなたの精神的な力を動員するために、あなたはあなた自身の能力を信じる必要があります。